東京・八王子市にある高尾山は、都心から約1時間で行ける手軽な山として人気で、年間300万人以上が訪れます。
ミシュランの旅行ガイドで最高評価(三つ星)に選ばれた経歴もあり、その知名度は世界的です。
しかし人気が高い分、週末や紅葉シーズンには登山道や山頂が人で埋め尽くされるほどの大混雑になることもしばしばです。
高尾山を快適に楽しむためには、混雑するタイミングと空いている時間帯を把握し、上手に計画を立てることが大切です。
本記事では2025年最新の情報に基づき、高尾山の混雑予想(いつ混むのか)と穴場時間、おすすめの登山コースまで詳しく解説します。
目次
高尾山混雑予想:ピーク時期と穴場時間
高尾山の混雑状況は一年を通じて大きく変動し、訪れる時期や時間帯によって様子が大きく異なります。
まずは、特に混雑が激しい繁忙期と、比較的ゆったりと楽しめる閑散期や穴場の時間帯について最新の傾向を見ていきましょう。
混雑のピークと繁忙期
高尾山が最も混雑するのは、紅葉シーズンや大型連休などの繁忙期です。
特に11月の週末・祝日は紅葉目当ての登山客で毎年大混雑となり、山頂から麓まで人の列が途切れないほどになります。
春のゴールデンウィーク期間(4月末~5月初め)も多くの人出で賑わい、2025年のGWは最大11連休となったことから例年以上の人波が押し寄せました。
また年末年始には初詣客が集中し、元旦にはご来光(初日の出)を拝むため深夜から登る人もいて早朝から山頂は身動きが取れないほどです。
では、ピーク時の高尾山がどれほどの混雑か、具体例を見てみましょう。
- ケーブルカー待ち時間が60分以上になることもあります。
ピーク時には2~3時間待ちの例もあります。 - 1号路の登山道は、渋谷のスクランブル交差点のように人で埋め尽くされ、自分のペースでは歩けません。
- 山頂はレジャーシートを広げる場所もないほど混み合い、トイレも長蛇の列です。
- 名物のとろろ蕎麦など山頂・中腹の飲食店も、混雑時は長時間待ちが発生することもあります。
このように紅葉時期や大型連休の高尾山は「登山」というより「行列」に近い状況です。
さらに2月3日の節分祭など特定イベントの日も、平日でも麓の薬王院に参拝客が殺到することがあります。
一年の中で混雑がピークとなる繁忙期を把握し、その時期を避けることが混雑回避の第一歩になります。
閑散期と狙い目のシーズン
反対に、観光客が少なめでゆったり過ごせる閑散期も存在します。
真冬や梅雨時などは登山客が減り、高尾山の自然を静かに満喫できる絶好のチャンスです。
以下に比較的空いている狙い目の時期をまとめました。
- 真冬(1月中旬~2月):空気が澄み、平日なら人影もまばらです。
ただし山頂は非常に冷え込むため、防寒対策は必須です。 - 新緑の季節(5月末~6月):木々の緑が美しい初夏ですが、紅葉シーズンほど混雑しません。
- 夏休み後半(8月下旬):お盆を過ぎると人出が落ち着き、登山客は比較的少なくなります。
- その他のオフシーズン:3月(春休み前)や梅雨(6月中旬~7月上旬)も狙い目です。
例えば2月は節分の日を除けば土日でも穏やかで、快適に登山を楽しめます。
新緑が爽やかな5月下旬~6月や、観光客が少ない真冬の平日などは、高尾山の静けさを味わうには最適なタイミングです。
混雑する曜日・時間帯
混雑度は曜日や時間帯によっても大きく変わります。
予想通りではありますが、土日祝日は平日に比べ格段に人出が多くなります。
特に行楽日和の土曜日・日曜日は登山道もケーブルカーも大混雑で、平日との落差は「天国と地獄」と言えるほどです。
一方、平日は比較的空いており、仕事始めの月曜日などは登山客が少なく静かな山歩きを楽しめる傾向があります。
もちろん祝日と重なる大型連休(例えばシルバーウィークなど)は例外で、平日でも休日並みの混雑になるので要注意です。
高尾山が混雑する典型的な時間帯も押さえておきましょう。
- 上りピーク時間帯: 午前9時~11時頃
- 下りピーク時間帯: 正午過ぎ~午後2時頃
多くの人は午前10時前後に登り始め、昼頃に山頂へ到着して休憩し、その後下山を始めます。
そのため登りは午前中の遅い時間帯に混雑が集中し、下山はちょうどお昼過ぎから午後にかけてピークを迎えます。
この時間帯に合わせて行動すると、ケーブルカー乗車から山頂滞在まで常に人混みに巻き込まれることになりかねません。
空いている穴場の時間帯
では、混雑を避けるには具体的にどの時間帯を狙えば良いのでしょうか。
結論から言えば「できるだけ早い時間」に動くのが効果的です。
例えば週末しか行けない場合でも、朝一番のケーブルカー(始発は8時頃)に乗るか、早朝に登り始めて10時前には山頂に到着してしまえば、その後の大混雑を尻目にゆとりを持って行動できます。
逆に午後遅めの時間帯も比較的空いています。
多くの登山者は午後3時頃までには下山を完了するため、それ以降の登山道は次第に人が減って静かになります。
夏場で日没が遅い時期であれば、夕方から登って夜景を楽しむという手もあり、昼間とは違った静かな高尾山を味わえます(ただし最終ケーブルカーの時間や懐中電灯の準備には注意)。
さらに天候も混雑に影響します。
雨が降りそうな日や小雨の日は敬遠する人が多いため、天候を気にしないのであれば狙い目です。
多少の雨であれば木々が雨を遮り、しっとりとした森の空気の中を静かに歩くことができます。
例えば、真冬の平日早朝に登れば、高尾山をほぼ独り占めすることもできます。
小雨交じりの日ならなおさら静かで、鳥のさえずりしか聞こえないような贅沢な体験ができるでしょう。
高尾山で混雑を回避するためのポイント
ここまで、高尾山が混雑する時期や時間帯とその逆の穴場について見てきました。
続いては、これらの情報を踏まえて実際に混雑を避けるための具体的なポイントや工夫を紹介します。
少しの心がけで、高尾山登山がぐっと快適になります。
訪れる曜日・時期を工夫する
まず何より効果的なのは、「いつ行くか」を工夫することです。
可能であれば土日祝日ではなく平日に訪れるだけで、混雑具合は大きく緩和されます。
限られた休みをやりくりする必要はありますが、平日の静けさは週末とはまるで別世界と言っても過言ではありません。
また訪問時期そのものをずらすことも有効です。
例えば紅葉シーズンの喧騒を避け、初夏の新緑が美しい時期や真冬の澄んだ空気の時期に行けば、景色を楽しみつつも人出はぐっと少なくなります。
実際、新緑が映える5月下旬~7月上旬や空気の澄んだ1月中旬~2月は、紅葉の繁忙期ほどは混雑しません。
「紅葉にこだわらない」のも賢い選択で、違った季節の高尾山ならではの魅力も発見できるでしょう。
どうしても紅葉の時期しか行けない場合は、せめて平日を選ぶ、連休を避けるなど、可能な範囲でベストな日を選びましょう。
シーズンと曜日の選択ひとつで、登山当日の混雑度は大きく変わってきます。
早朝・夕方に時間帯をずらす
次に、登山開始時間をずらす工夫です。
混雑日は「いかに他の人より先に動き出すか」が鍵になります。
例えば紅葉シーズンの週末でも、朝早く行動すれば混雑を大幅に回避できます。
始発のケーブルカーに乗って8時台に山頂に着く、もしくは7時頃から歩き始めれば、10時過ぎに登山客が押し寄せてくる頃には下山に移れている計算です。
逆に午後遅めの時間帯を狙う方法もあります。
日中のピークを避け、あえて13~14時頃に高尾山口駅をスタートすれば、上りの大混雑はほぼ収まった後になります。
夕方以降は下山客も減り静けさが戻りますので、ゆっくり登って夕暮れ時の山頂に到着するようなプランも可能です。
特に夏場は日が長く、17時台でも明るさがありますので、人が少なくなった山頂から都心の景色を眺めたり、ゆっくりと下山したりといった楽しみ方もできます。
ただし、遅い時間に登る場合は下山時刻に注意が必要です。
ケーブルカーやリフトの最終運転時刻(季節や曜日によって変動)を確認し、万が一逃した場合に備えて懐中電灯を持参しましょう。
冬季は17時前後には日が暮れますので、安全確保のため無理のない計画を心がけてください。
リアルタイム混雑情報を活用する
事前に混雑状況を把握しておくことも有効です。
現在の高尾山の様子を知るには、SNSや地図アプリなどが役立ちます。
例えば登山当日の朝にツイッターで「#高尾山混雑」などのハッシュタグ検索をすると、他の登山者が投稿したケーブルカーの行列状況や山頂の写真など、リアルタイムな情報が得られます。
またGoogleマップで「高尾山口駅」や「清滝駅(ケーブルカー乗り場)」を検索すると、時間帯別の混雑状況グラフを見ることができます。
これは現地の訪問データに基づくもので、「〇時頃に最も混み合う」といった傾向を視覚的に把握できる便利なツールです。
その情報を参考に出発時間を前倒ししたり、逆にピークを過ぎるまで待ってから出発するなど、予定を調整することもできます。
さらに、高尾山口駅前にはライブカメラが設置されており、インターネットで映像を確認可能です。
現地のリアルな人出の様子を映像で掴めるため、「今日は思ったより空いていそうだ」「既にケーブルカー乗り場に行列ができている」など事前に判断する材料になります。
これらのリアルタイム情報を上手に活用し、混雑を予測・回避しましょう。
混雑時のケーブルカー・リフト対策
高尾山の麓から中腹にかけてはケーブルカーとリフトが運行しており、多くの観光客が利用します。
そのため混雑日はケーブルカーの駅(清滝駅・高尾山駅)で長い行列ができるのが常ですが、混雑対策としてリフトを活用する方法があります。
リフト(山麓駅~山上駅)は開放的な2人乗りの椅子式で、ケーブルカーに比べ利用者が少ない傾向があります。
所要時間はケーブルカーと大差なく、木々の間を抜ける爽快感も味わえるため、並ぶ時間を短縮しつつ自然も満喫できる穴場的な移動手段です。
また、体力に自信がある場合は思い切って麓から山頂まで歩いてしまうのも有効です。
ケーブルカー待ちで1時間列に並ぶくらいなら、その時間で1号路を歩いて登れてしまいます。
実際、混雑期には「列に並ぶくらいなら歩いた方が早い」と途中で歩き始める人も少なくありません。
下りに関しても同様で、降りのケーブルカーが激混みの場合は徒歩下山に切り替えたほうがストレスなく麓まで戻れるでしょう。
どうしてもケーブルカーを利用したい場合は、下山時刻の調整がポイントになります。
前述の通り正午~午後2時前後は下りのケーブルカーが最も混雑する時間帯です。
このピークを避け、少し早めの午前中に下山を開始するか、あるいは思い切って山頂で夕方までゆっくり過ごして時期をずらせば、待ち時間を大幅に短縮できます。
例えば紅葉シーズンでも、朝一番のケーブルカーで上り、下山は15時過ぎにしたところ待ち時間ゼロだった、といったケースもあります。
なお、車でアクセスする場合は駐車場の混雑にも注意が必要です。
高尾山口駅周辺の駐車場は週末朝には満車になることが多いため、公共交通機関(京王線の高尾山口駅直通電車など)の利用がおすすめです。
道路も紅葉時期の連休には渋滞しますので、時間に余裕を持って行動しましょう。
混雑回避に役立つ高尾山のおすすめ登山コース
最後に、コース選びの観点から混雑を避ける方法を見てみましょう。
実は高尾山には複数の登山ルートが存在しますが、観光客の多くはメインの1号路とケーブルカー沿いのルートに集中します。
言い換えれば、それ以外のコースを選択すれば人混みを大幅に避けられる可能性があります。
ここでは混雑回避に役立つおすすめの登山コースをいくつか紹介します。
1号路(表参道):最も混雑する定番ルート
「表参道」とも呼ばれる1号路は、高尾山で最もメジャーなコースです。
麓の清滝駅から山頂の薬王院に至るまで全区間が舗装されており、傾斜も緩やかで歩きやすいため、初心者や観光目的の人々にも人気があります。
その反面、土日祝日ともなると登山客が集中し、幅広の山道が人で埋め尽くされてまるで初詣の参道のような状態になります。
1号路沿いには途中に見晴らし台や紅葉台、名物の権現茶屋(天狗焼きが有名)やサル園・野草園など観光スポットも点在しています。
また山頂手前には高尾山薬王院という由緒あるお寺があり、多くの参拝客で賑わいます。
このように見どころ豊富な反面、観光客が集中するため常に混雑しがちです。
「高尾山=1号路」と考える人も多い定番ルートですが、混雑を避けたい場合はこの1号路をあえて外し、他のコースに挑戦してみることをおすすめします。
稲荷山コース:静かで自然豊かな裏道
稲荷山コースは、高尾山口駅から1号路とは反対側の尾根伝いに山頂を目指す登山道です。
スタートからしばらく急な上りが続きますが、途中からは土の山道が尾根沿いに延び、木々に囲まれた静かな雰囲気が味わえます。
舗装された1号路とは異なり、本格的な山歩きの感覚を楽しめるため、週末でも観光客は比較的少なめです。
稲荷山コースは高尾山の中級者向けコースと言われますが、ゆっくり休憩を挟みながら進めば特別な装備がなくても十分登頂可能です。
途中には展望の良いベンチや休憩所もあり、晴れた日には都心方面を望む絶景が広がります。
1号路のような人混みとは無縁で、聞こえるのは風の音や鳥のさえずりだけという区間もあります。
静かな環境で高尾山の自然を満喫したい方には、稲荷山コースは最適な選択肢でしょう。
6号路(琵琶滝コース):沢沿いを行く涼やかなルート
6号路は、高尾山の麓から沢沿いに山頂を目指す人気コースの一つです。
登山途中には修行の場として有名な琵琶滝があり、せせらぎの音と共に進むルートは夏でも涼感があります。
コース序盤から中盤にかけては小川沿いの細い山道が続き、所々で石や木の根を跨ぎ越す箇所もあります。
舗装がない分1号路より登山らしい雰囲気を味わえますが、その分観光客はやや少なめです。
勾配は一部急な箇所もありますが、全体としては稲荷山コースと同程度の難易度で、足元に気を付ければ初心者でも挑戦可能でしょう。
特に早朝や平日は静かで、清流のせせらぎや木漏れ日を独り占めできます。
雨の翌日はぬかるみや滑りやすい箇所があるため注意が必要ですが、マイナスイオンたっぷりの自然を満喫できる6号路は、穴場的なおすすめルートです。
裏高尾ルート:上級者向けの静寂な道
裏高尾ルートとは、高尾山の裏側(北側)から山頂を目指す幾つかの登山ルートの総称です。
日影沢や小下沢などのエリアから取り付くコースがあり、これらは表側に比べて利用者が格段に少ないのが特徴です。
登山道は未整備の箇所も多くアップダウンも大きいため経験者向けですが、その分“一人じめ”感の高い静かな山歩きが楽しめます。
裏高尾コースを使う場合、高尾山口駅からではなく別の登山口までバスなどでアクセスする必要があります。
例えば日影沢キャンプ場方面からのルートは、雑木林の中を進み途中で沢沿いを登って山頂近くに合流する道です。
途中に茶屋やトイレはありませんが、人の気配がほとんどない森の中で野鳥や季節の草花を観察しながら登ることができます。
しっかりとした装備と地図を携行すれば、高尾山の奥深い自然を堪能できる穴場コースとして上級者に人気があります。
まとめ
以上、高尾山の混雑予想情報と穴場時間、そしておすすめの登山コースについて詳しく解説しました。
首都圏随一の人気を誇る高尾山は混雑しがちですが、事前に傾向を知りちょっと工夫するだけで快適さが大きく向上します。
ピークの時期・時間帯を避ける、平日や早朝を狙う、ルート選びを工夫するといったポイントを押さえておけば、人混みを避けつつ高尾山の豊かな自然と絶景を満喫できるでしょう。
2025年現在の最新動向を踏まえた情報を参考に、ぜひ賢く計画を立てて、快適で思い出に残る高尾山ハイクを楽しんでください。
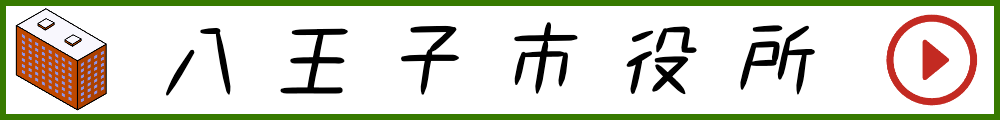 八王子市役所
八王子市役所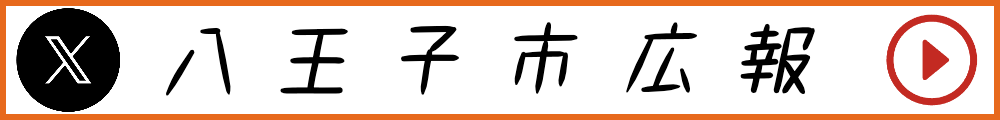 八王子市広報
八王子市広報
コメント